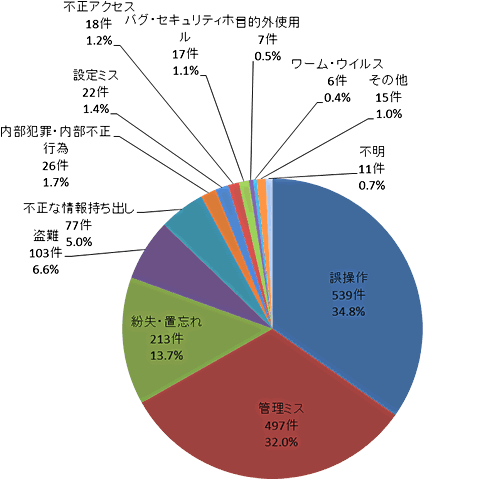診療予約システムをお探しですか?
それでは、早速はじめましょう!
今回は予約優先制のクリニックが「時間帯予約制」に運用変更する際に予約システムがはたす役割について書いてみたいと思います。
1. 予約優先制をやめるために診療予約システムができること
予約優先制から時間帯予約制に移行するには、予約優先という考え方を捨てなくてはなりません。仕組みだけ時間帯予約制の運用に変えても、予約優先という考え方が残ってしまっては、残念ながら問題の根本的な解決ができないのです。なぜなら、予約優先という考え方が残ってしまうと、結局患者さんの待ち順が固定されないため、予約優先制で必ず発生する問題を消すことができないからです。
これを解決するには、同じ時間帯の枠に受付けた患者さんは、受付順に順番を固定してしまう必要があります。
例えば、下記のようなケースを考えてみましょう。
・30分ごとに5名の枠で予約を取っているクリニック
・9:00に5名予約が埋まっている。
・9:30に予約が1名いる。
この場合、時間帯予約制の運用では9:10に予約なしの患者さんが来院すると、10:00の枠に受付を行います。10:00の枠には予約者がいますが、当然まだ来院していませんので、さきほどの予約なしの患者さんが10:00の時間帯の1番目として順番を付与してしまいます。
予約者はもしかしたらキャンセルになるかもしれませんし、いつ来るかもわかりません。一方、予約なしの患者さんはもう来院していますので、診察することが確定しているわけです。よって、時間帯予約制では、予約なしの患者さんも来院時点で順番を確定してしまうのです。これは、予約なしの患者さんが来院して10:00の空枠に予約を入れたと考えればよく、それであれば順番が1番目でも何の問題もないはずです。前提として、時間帯予約制は9:30~10:00の予約というように時間に幅のある予約として患者に案内する必要がありますが、これさえクリアしておけば予約者を優先する必要はありません。
そこで「診療予約2013」では、同じ時間帯の患者さんは来院順に待ち順が付与されるようになっています。このおかげで予約の有無にかかわらず、待ち順が固定されることになります。この仕組みによって、予約を優先するために順番が固定できないという予約優先制の問題をクリアすることができるようになっているのです。
2. 予約比率を高めるために診療予約システムができること
時間帯予約制のメリットである来院時刻の平準化のためには、予約比率を高めることが必要です。なぜなら予約比率が低いままだと、患者さんは混む時間帯に集中して来院してしまうかもしれないからです。一方で、予約比率を高めると、そのぶん予約受付業務が増えてしまいます。そのため、現在のスタッフ数を変えずに予約比率を上げていくためは、スタッフの協力を仰がなければなりません。
しかし、診療予約システムでネット予約を活用すれば、スタッフの負荷を最小限にして予約比率を上げていくことができます。患者さんは「電話予約」「次回予約」「ネット予約」「直接来院」の4つのパターンで来院されることになりますので、ネット予約比率を上げることでスタッフの負荷を下げることができます。ネット予約の比率は診療科目などによって違いますが、30~70%ぐらいになります。また、次回予約は従来どおりですので負荷が増えるということはありません。さらに、直接来院は必ず一定数残りますので、残りが電話予約になります。うまくいけば、電話予約の比率は10%以下に抑えられます。これであれば、あまり負荷をかけずに予約比率を上げられるのではないでしょうか。
今回は、予約優先制から時間帯予約制に運用変更する際に、診療予約システムができることについてまとめてみました。もし、予約優先制で待ち時間の問題が発生し、クレームが起こっているようであれば、是非時間帯予約制への移行をご検討ください。「診療予約2013 時間帯予約版」は時間帯予約制の運用のためにつくられた予約システムですので、きっとお役に立てるはずです。
それではまた、次回のエントリーで。
ツイート、いいね!していただけると嬉しいです!
過去記事: 過去の記事一覧はこちらから
関連記事: 予約優先制のクリニックで待ち時間が長くなるメカニズム
関連記事: 知っている医師は始めている、時間帯予約制で待ち時間を減らす方法。
関連記事: 診察効率の向上策としての時間帯予約制のすすめ
キーワード: 予約優先制,当日順番待ち,事前予約,業務フロー,制度変更