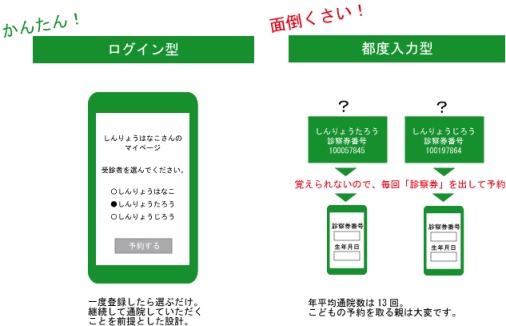診療予約システムをお探しですか?
それでは、早速はじめましょう!
前回のエントリーで、予約優先制をとっていると必ず発生する問題についてまとめました。今回は、その解決策としてふれた「時間帯予約制」の運用について書いてみたいと思います。
まず予約優先制と時間帯予約制の違いを理解するために、運用の違いを箇条書きにしてみます。
■ 予約優先制
・時間指定の予約
予約者は、「10:00の予約」などきっちり時間が決まっているものとして来院する。
・予約を優先
予約者は予約時間がきたら優先的に診察され、予約なしの患者はその間に診察となる。
・予約者リストと順番待ちの列の2列で管理
予約ありと予約なしの患者はそれぞれ別で管理する。
■ 時間帯予約制
・時間帯の予約
予約者は、「10:00~10:30の予約」のように幅をもたせた時間帯で予約をしているものとして来院する。
・予約優先ではない
予約なしの患者は、空いている直近の予約枠にあたかも予約を取ったかのように受付する。同じ時間帯内では予約ありを優先しなくてもよく、受付順で診察する。
・予約者と順番待ちを1列で管理
予約ありと予約なしの患者は、受付時点で同じ列で管理する(予約表で一元管理)
予約優先制では、予約者と順番待ちの列を別々で管理しているため、各患者さんの待ち時間を計算できません。なぜなら、予約者と順番待ちの列を状況に合わせて”やり繰り”しているため、患者さんの順番は固定されず常に変動する可能性があるからです。この「状況に合わせてやり繰りする」部分が予約優先制の問題の本質であり、患者さんのクレームが起こる原因となるものです。
そこで時間帯予約制では、予約のあり・なしに関わらず、来院した時点で「その時間帯内の順番」を付与してしまいます。そうすることで来院している患者さんすべての待ち時間が計算できるようになると同時に、待ち時間が異常に長くなることを防ぐことができるようになります。なぜなら、待ち時間が異常に長くなるのは、予約者を優先するために予約なし患者の「順番」を変動させていることが原因だったからです。
予約優先制というのは、患者の数が少ないうちはうまく運用できますし、予約をしてくれた患者さんを優先的に診察してあげたいという考え方や気持ちには共感します。しかし、患者さんが増えてきたときにはその「予約者を優先したい」という善意が、むしろ患者さんの待ち時間を長くしたり、クレームを生む原因となってしまうのです。
考え方を変えると、予約優先制で「待ち時間の問題が顕著になってきた」「クレームが増えてきた」というのはポジティブなメッセージでもあります。つまり、患者さんが増えなければ、予約優先制でも十分運用できるわけですから、それがうまくいかないということは、患者さんの数が閾値を超えたことを意味するからです。そして、たくさんの患者さんに必要とされ、次のステージに上がる必要のあるクリニックにとって、時間帯予約制は最も適した運用であると思います。
時間帯予約制というのは知っている人は知っていますが、知らないと一見運用しづらそうに感じます。しかし、基本的にはとてもシンプルな運用ですので、もし予約制で待ち時間の問題に悩まれている場合は、ぜひ導入を検討してみてください。ちなみに運用変更は診療予約システムを利用しなくてもできますが、「診療予約2013 時間帯予約版」をご利用いただけるとよりスムーズに移行できます。ここに紹介しきれない詳しい運用方法などをご提案させていただきますので、ぜひ当社までお問合せください。
それではまた、次回のエントリーで。
ツイート、いいね!していただけると嬉しいです!
■ 時間帯予約制の詳細はこちらのスライドでチェック!
関連記事: 待ち時間対策のために予約システムができること
関連記事: 予約優先制のクリニックで待ち時間が長くなるメカニズム
関連記事: 診察効率の向上策としての時間帯予約制のすすめ
過去記事: 過去の記事一覧はこちらから
キーワード: 予約優先制,時間帯予約,受付順番制,うまい運用,ケース,事例,解説,原因,乗り換え,変更,ハイブリッド予約,アイチケット